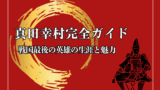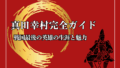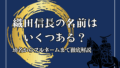関ヶ原の戦いで西軍に与し敗北した真田昌幸・信繁父子は、慶長5年(1600年)から14年間という長期にわたり九度山での蟄居生活を余儀なくされました。
この期間は信繁(幸村)の生涯で最も長い時間を一つの場所で過ごした貴重な時代でもあります。史料から明らかになったのは、一般的に語られる「武芸に励む雌伏の日々」とは異なる、経済的困窮と家族愛に満ちた人間味溢れる生活実態でした。
この記事では、昌幸の書状や信繁の手紙などの一次史料を基に、父子の日常生活から心境の変遷、そして「日本一の兵」へと至る精神的成長の軌跡を詳細に追跡します。
九度山蟄居の背景

※「蟄居(ちっきょ)」とは、江戸時代の武士などが過失を犯した際に科された刑罰で、自宅にこもって謹慎すること。現代では引きこもりの意味にも使われます。
関ヶ原の戦い敗北から流罪まで

西軍敗北と死罪宣告
慶長5年(1600年)9月15日、関ヶ原の戦いで石田三成率いる西軍が敗北。真田昌幸・信繁父子は西軍に与していたため、徳川家康により死罪を宣告された。父子は上田城で徳川秀忠の西上を阻止し、秀忠を関ヶ原の戦いに間に合わせなかった功績が、かえって家康の怒りを買う結果となった。
真田信之の助命嘆願
東軍に属していた長男・真田信之(信幸)は、舅である本多忠勝とともに家康に必死の助命嘆願を行った。信之の妻は忠勝の娘であり、また信之自身の戦功もあって、ついに家康は死罪を流罪に減じることを決断した。
高野山蟄居から九度山移住へ
同年10月9日、真田父子は真田家の菩提寺である高野山蓮華定院に身を寄せた。昌幸53歳、信繁33歳の時である。しかし高野山は女人禁制であり、信繁の妻・竹林院との生活ができないため、間もなく高野山麓の九度山に移住することとなった。
なぜ九度山が選ばれたのか
高野山の政治的中立性
高野山は古来より政治的中立を保つ宗教的聖地であり、流罪地としては適切とされた。また真田家は蓮華定院と深い関係を持っていた。
紀州徳川家の監視体制
九度山は紀州徳川家の領地に近く、監視が容易であった。定期的な身元確認や行動制限を行いながらも、比較的自由な生活を許可した。
交通の要衝としての立地
九度山は高野山への参詣路の要衝であり、情報の収集や外部との連絡が可能であったが、同時に監視も行き届いていた。
九度山到着と初期の生活
慶長5年(1600年)12月の移住
父子での旅路
高野山から九度山への移住は、冬の寒さが厳しい時期に行われた。昌幸と信繁は簡素な荷物とともに、山道を下って九度山の地に足を踏み入れた。
従者・家臣の同行者
上田から随行した池田綱重、原出羽守、小山田治左衛門など16名の家臣が同行。比較的多くの従者を連れることが許されたのは、助命嘆願の効果でもあった。
生活基盤の確立
住居の確保と改修
現在の真田庵(善名称院)の場所に屋敷を構えた。当初は簡素な建物であったが、徐々に生活に必要な設備を整え、家族での生活に適した環境を作り上げた。
地元住民との関係構築
九度山の住民たちは、当初は流罪人である真田父子を警戒していたが、その人柄や礼儀正しさから次第に信頼関係を築いていった。特に地元の商人や職人との関係は良好であった。
収入源の確保努力
兄・信之からの仕送りが主な収入源であったが、それだけでは不十分であった。後に竹林院が考案した真田紐の製造・販売が重要な収入源となった。
蟄居生活の実態
日常生活のスケジュール
朝の起床から昼まで
早朝の起床後、仏前での読経、朝食。その後は軍学の研究や武芸の鍛錬に励んだ。
学問・武芸の日課
兵術や天文学の学習、武田流兵法の研究、息子・大助への教育指導を行った。
夜の就寝まで
家族との団欒、連歌や和歌の作成、時事についての思索に時間を費やした。
経済状況と家計管理
史料に見る困窮生活
「なほなほ、銀子二匁目出珍重に候。度々尊礼に預り候。恐悦の至に候…」
– 慶長8年3月15日 信綱寺宛真田昌幸書状より
兄・信之からの仕送り
真田信之からの定期的な仕送りが生活の基盤であったが、昌幸の書状には度々金銭を催促する内容が見られ、慢性的な資金不足に悩んでいたことがわかる。
質素な食生活の実情
「当冬は万(よろず)不自由にて一入(ひとしお)うそざぶく」という信繁の書状からも、特に冬季の生活の厳しさが伺える。
住居と生活環境
善名称院(真田庵)での生活
現在の真田庵の敷地に屋敷を構え、昌幸・信繁・竹林院・大助らが共同生活を営んだ。敷地内には昌幸を祀る真田地主大権現や雷封じの井戸なども設けられた。
間取りと家族の居住空間
武士の格式を保ちながらも質素な造りで、昌幸の居間、信繁夫婦の部屋、子供たちの部屋、家臣の詰所などが配置されていた。
季節ごとの生活の変化
春は高野山参詣、夏は紀ノ川での水練、秋は連歌会、冬は読書と学問に専念するなど、季節に応じた生活リズムを確立していた。
真田昌幸との父子関係

共同生活での学び
昌幸からの軍学指南
武田信玄の薫陶を受けた昌幸から、武田流兵法の神髄や築城術の理論を学んだ。後の真田丸建設にも活かされる知識である。
政治・外交の知識継承
昌幸の豊富な外交経験から、大名間の駆け引きや情勢分析の手法を学び、後の大坂の陣での活動に生かした。
謀略術の伝授
「表裏比興」と呼ばれた昌幸の謀略術や情報収集の手法を伝授され、信繁の戦略眼を育成した。
父子の心境の変化
初期の絶望から諦観へ
蟄居当初は復帰への強い願望があったが、時間の経過とともに現実を受け入れ、九度山での生活に順応していった。
復活への希望と現実
昌幸は常に天下の情勢を分析し、徳川への復讐の機会を窺っていたが、現実的な困難さも理解していた。
晩年の達観境地
昌幸の晩年は病気がちとなり、「十余年存じ候儀も、一度面上を遂げ候かと存じ候処、只今の分は成り難き望に候」という諦観の境地に達していた。
慶長16年(1611年)昌幸の死
病床での最期の教え
昌幸は6月4日に65歳で病没。信之宛の最後の書状では「養生の儀油断無く致し候間、目出度く平癒致し、一度面談を遂ぐべく存じ候間、御心安かるべく候」と記している。
葬儀と墓所の設営
昌幸の死後、本多正信は「昌幸は流罪人であり公儀御憚りの仁」として、幕府の許可を得て弔うよう信之に諭した。墓所は現在の真田庵境内に設けられた。
家族生活の詳細
竹林院との夫婦生活
結婚生活の実情
大谷吉継の娘である竹林院は、信繁の正室として九度山での困窮生活を支えた。夫婦の絆は逆境の中でより深まり、5人の子供をもうけた。
困窮下での夫婦の絆

経済的困窮の中でも、竹林院は真田紐の考案や家計の管理で家族を支え、信繁との強い信頼関係を築いていた。
「真田ひも」は、戦国武将・真田家に由来する日本の伝統的な平ひもです。切れにくくほどけにくい特性から、武具や甲冑の固定に用いられました。その丈夫さは「粘り強く戦う真田家」の姿とも重なり、縁起の良いひもとして庶民に広まります。江戸時代には刀の下げ緒やたばこ入れに使われ、現代でも和装小物や贈答品を彩る実用的で美しい存在として親しまれています。
子供たちの成長記録
大助(幸昌)の教育方針
慶長7年(1602年)九度山で生まれた長男・大助には、武芸と学問の両面から厳格な教育を施した。父とともに紀ノ川で水練を行い、将来の武将としての資質を育成した。
娘たちの躾と将来への配慮
娘たちには武家の女性としての教養を身につけさせ、将来の結婚に備えた教育を行った。茶道や和歌、裁縫などの技能を習得させた。
家族団欒の時間
夕食後は家族全員で連歌や和歌を楽しみ、昌幸から戦国時代の思い出話を聞く時間を大切にしていた。
年中行事と季節の楽しみ
春
正月の祝い事、高野山参詣、花見での和歌会
夏
紀ノ川での水練、七夕の節句、避暑での読書
秋
月見の宴、連歌会の開催、収穫への感謝
冬
年末年始の行事、囲炉裏での団欒、学問研究
地域社会との関わり
九度山の人々との交流
地元住民からの支援
当初は警戒されていた真田父子だったが、その人柄や礼儀正しさから次第に地元住民の信頼を得た。特に困窮時には食料や日用品の差し入れを受けることもあった。
商人・職人との関係
真田紐の製造では地元の職人の技術指導を受け、販売では商人のネットワークを活用した。これにより相互に利益をもたらす関係を築いた。
地域社会への貢献
信繁は地元の子供たちに読み書きを教えたり、病人の看病を手伝うなど、積極的に地域社会に貢献し、住民からの敬愛を集めた。
高野山との関係
蓮華定院での菩提
真田家の菩提寺である蓮華定院との関係は継続し、定期的に参詣を行った。昌幸の葬儀も蓮華定院で執り行われた。
僧侶たちとの交流
高野山の僧侶たちとの学問的な交流を深め、仏教哲学や連歌について議論を交わした。これが信繁の精神的支えとなった。
紀州藩の監視体制
紀州徳川家による監視はあったが、比較的緩やかであった。定期的な身元確認や行動報告は求められたが、日常生活への過度な干渉はなく、真田父子は相対的に自由な生活を送ることができた。
学問・武芸の研鑽
軍学の継続研究
武田流兵法の深化
昌幸から受け継いだ武田流兵法をさらに深く研究し、築城術や戦術理論の理解を深めた。
築城術の理論研究
後の真田丸建設に活かされる築城理論を学び、地形を活かした防御戦術を研究した。
戦術書の著述
自らの軍学研究をまとめ、後世に残すための戦術書の執筆を行った。
文学・和歌への傾倒
連歌への情熱
史料によると、信繁は九度山時代に連歌に夢中になっており、これが心の慰めとなっていた。「其の元連歌しうしんと承り及び候。此の方にても徒然なぐさみに仕り候へとすゝめられ候」という記述からも、連歌への深い関心が伺える。
武芸の鍛錬継続
槍術の日常練習
毎日の槍術練習を欠かさず、息子の大助とともに技術向上に努めた。将来への備えとして武芸の錬磨を継続した。
体力維持の工夫
紀ノ川での水練や山歩きを通じて体力を維持し、48歳で大坂城に入城した際も十分な戦闘能力を発揮できた。
外部との秘密連絡
豊臣家との水面下の接触
真田紐の行商を通じて、全国各地の情報を収集するとともに、豊臣家との秘密の連絡も維持していたとされる。慶長19年(1614年)に豊臣秀頼からの使者が九度山を訪れ、大坂城入城を要請したのも、このような関係があったからこそである。
全国の浪人たちとの情報交換
真田紐の行商により、各地の反徳川勢力や浪人たちとの情報ネットワークを維持し、天下の情勢変化を常に把握していた。
兄・信之との書簡交換
信之との間では定期的に書簡を交わし、家族の近況報告のほか、政治情勢の分析や将来への相談も行っていた。信之の病気回復を喜ぶ書状なども残されている。

心境の変遷
蟄居初期(1600年~1605年)
絶望と屈辱感
関ヶ原敗北の衝撃と流罪への屈辱感で精神的に苦しんでいた。
復活への強い願望
必ずや徳川への復讐を果たすという強い意志を燃やしていた。
中期(1605年~1610年)
諦観と受容
現実を受け入れ、九度山での生活に順応していく心境となった。
家族生活への専念
妻子との生活を大切にし、子供の教育に力を注ぐようになった。
後期(1610年~1614年)
再起への機会窺い
豊臣家の危機を察知し、再び世に出る機会を模索していた。
最後の決断準備
大坂城入城への決断を固め、14年間の蟄居生活に終止符を打つ覚悟を決めた。
九度山脱出の決断
大坂冬の陣への参戦決意
豊臣家からの招集
慶長19年(1614年)春、豊臣秀頼の使者が信繁の庵を訪れ、徳川家を滅ぼすための協力を申し出た。招集には黄金200枚、銀30貫という破格の手付金が用意されていた。
家族との別れの覚悟
信繁は妻子を九度山に残し、長男・大助のみを連れて大坂城に向かう決断を下した。
14年間の集大成への意気込み
九度山で蓄積した軍学の知識と武芸の技能を、最後の戦いで発揮する意気込みに燃えていた。
慶長19年(1614年)10月の脱出
密かな準備と計画
10月9日深夜、紀州藩の監視の目をくぐって九度山を脱出。地元住民の協力も得て、秘密裏に脱出の準備を進めていた。
九度山からの脱出経路
真田古墳の抜け穴伝説もあるが、実際は夜陰に乗じて通常の道路を使って脱出したと考えられている。
大坂城への向かう道中
10月13日に大坂城へ入城。途中、各地の同志たちと合流し、総勢数百名の軍勢となって大坂城に到着した。
九度山時代の歴史的意義
戦国武将の隠遁生活の典型
真田父子の九度山での生活は、戦国時代末期の流罪武将の生活実態を示す貴重な史例であり、当時の社会状況や価値観を理解する上で重要な意味を持つ。
真田信繁の人格形成への影響
14年間の蟄居生活は、信繁の忍耐力と精神力を鍛え、家族愛を深化させ、民衆への理解を促進した。これらの経験が後の「日本一の兵」としての活躍の基盤となった。
現代への教訓
逆境に屈しない生き方の模範、家族の絆の重要性、希望を失わない精神力など、現代にも通じる人生の教訓を示している。
九度山ゆかりの史跡案内
真田庵(善名称院)
現在の境内と建物
真田父子の屋敷跡に建てられた寺院で、真田地主大権現、雷封じの井戸、昌幸・信繁の墓碑などがある。春にはボタンが咲き乱れ、美しい景観を楽しめる。
真田宝物資料館
境内には真田家ゆかりの資料を展示する宝物資料館があり、九度山時代の生活用品や書状などの貴重な史料を見学できる。
九度山・真田ミュージアム
展示内容と見どころ
真田昌幸、信繁、大助の真田三代の軌跡を、パネル展示とドラマ仕立ての映像で紹介。14年間の九度山での生活を詳細に解説している。
蟄居生活の再現展示
当時の住居や生活用品を再現し、真田父子の日常生活を体験できる。
体験プログラム
真田紐織り体験や甲冑の試着体験など、楽しく学べるプログラムが充実。
真田古墳と周辺史跡
散策コースの案内
真田古墳から真田庵まで約10分の散策コース「真田のみち」では、真田父子の足跡を辿りながら歴史を感じることができる。抜け穴伝説の残る真田古墳も必見。
地元案内人の活用
九度山観光協会では、地元の案内人による詳細な史跡案内を実施。
季節ごとの楽しみ方
春のボタン、夏の緑陰、秋の紅葉、冬の雪景色と四季それぞれの美しさを楽しめる。
観光情報
アクセス
南海高野線九度山駅から徒歩約10分
営業時間
9:00~17:00(最終入場16:30)
入場料
大人500円、小・中学生250円
休館日
月・火曜日(祝日の場合は営業)
まとめ

真田昌幸・信繁父子の九度山での14年間は、単なる流罪の期間ではなく、信繁にとって人間としての成長と武将としての完成を遂げる重要な時期でした。
経済的困窮や政治的な制約の中でも、家族の絆を深め、学問と武芸を研鑽し、地域社会との良好な関係を築いた真田父子の生き様は、現代においても多くの示唆に富んでいます。
九度山の史跡を訪れることで、「日本一の兵」と呼ばれた真田信繁の人間的魅力と、その源流となった蟄居時代の生活を体感することができるでしょう。