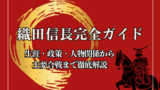こんにちは。(^o^)戦国時代大好き「お春」です。
今回は、織田家の忠臣、柴田勝家について考察します。当初は信長に期待をかけていなかった勝家が、どのように忠臣に変わっていくのか見ていきましょう。
織田信長への不信、そして忠臣へ変わるまで

信長の弟・信勝推しだった柴田勝家
柴田勝家は、織田家の重臣として名高い武将でしたが、その生い立ちや生年には多くの謎が残っています。若い頃から織田信秀に仕え、信秀の死後は信長の弟である信勝の家老として仕えてきました。
信長は若い頃は賢さよりその奇行が目立ち、周囲には「うつけ」と呼ばれており、柴田勝家もその評判を信じており、信長には期待していませんでした。
織田家を第一に考えた勝家は、信長の弟・信勝に家督を継がせるために挑戦するも、1556年の稲生の戦いで敗北を喫しました。
稲生の戦いで信長の実力を認めた後は、再び家臣としての地位を取り戻し、信長に忠誠を誓いました。
謝罪そして直属の家臣としての活躍
信長に一旦は不信感を示し、背いた勝家でしたが、信長の直属の家臣として活躍する機会を得ました。1568年、信長の先鋒として京に上洛し、南伊勢や近江などの合戦で武功を挙げました。
特に、1570年の長光寺城の戦いでは800もの首を挙げ、甕を割って将兵たちに覚悟を促す逸話から「甕割り柴田」として称されました。また、1571年の長島一向一揆との戦いでも勇敢に戦ったことが知られています。
豊臣秀吉との確執そして…
柴田勝家は活躍を続け、1575年には越前八郡49万石と北庄城を与えられ、北陸方面の軍司令官として加賀平定や上杉氏との戦いに挑みました。しかし、手取川の戦いで羽柴秀吉との意見の相違が露呈し、最期は1583年の賤ヶ岳の戦いで敗退しました。北庄城でお市と共に自害する運命をたどることとなりました。
柴田勝家の生涯は、信長への忠誠と武勇の精神が示されています。織田家を思う気持ちから信長に背くものの、謝罪し忠臣としての道を歩んでいく姿は、歴史に残る勇士として称賛されるべき存在と言えるでしょう。
柴田勝家から学べること
織田家への忠誠と信念
柴田勝家は信長に一旦は背きますが、最終的には信長に忠誠を誓い、武功を挙げていきます。背景には織田家を思う気持ちの強さと、こうと決めたら信念を曲げない気質があると考えます。
ここからは筆者の想像になるのですが、勝家の忠誠心は、信長への忠誠ではなく、織田家への忠誠、さらには長く仕えた信長の父・信秀への忠誠心だったのではないか?ということです。
稲生の戦いで信長の実力を目の当たりにすると、手のひらを返したように忠誠を誓うのですが、これも信長ではなく、織田家への深い忠誠心からだと考えます。
信長に背いたことも、手のひら返しも、織田家への忠誠心からきていて、強い信念を貫いていると考えます。
挫折や失敗をどうリカバリーするか
柴田勝家は一旦は信長に背きますが、再び信長に仕えることを選び許され、武功を挙げて結果を示しました。彼の姿からは、挫折や失敗をリカバリーする力、切り替えの大切さを教えられます。
落城前日にあっても一流
賤ヶ岳の戦いで敗れ北庄城が落城する前日には、残った一族郎党を集め最後の酒宴をもよおしたそうです。最後まで一流の武将であろうとした気概に驚かされます。