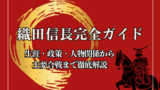織田信長と戦から、織田信長という人物像に迫っていきます。今回は家督を継いでから起きた「赤塚の戦い(あかつかのたたかい)」を取り上げます。
赤塚の戦いとは – 信長家督継承後の初合戦
織田信長は戦国時代に名を馳せた武将として広く知られていますが、そのすべての戦いが成功に満ちたものばかりではありませんでした。
今回は、家督を継いだばかりの若き信長にとって初めての戦い「赤塚の戦い(あかつかのたたかい)」について取り上げます。これは、リーダーシップが試される一方で、その課題が浮き彫りになった戦いでした。
信長の家督継承と周囲の不安
信長が織田家の家督を継いだのは、父・織田信秀の死後のことでした。信秀が存命中はその強力な影響力で周囲の勢力を抑えていましたが、彼の死により多くの不安が浮上しました。
信長が若く、周囲からもそのリーダーシップに疑問を持たれる中で、彼の初めての試練が「赤塚の戦い」でした。信長が家督を継いだばかりという背景から、彼の前途に多くの壁が立ちはだかっていたのです。
戦いの背景 – 山口教継の裏切りと今川氏との関係

今川氏の存在と斎藤氏との同盟
1552年に発生した赤塚の戦いでは、三河を実質的に支配下に置くなど勢いのある、駿河国の今川氏という強力な敵対勢力が存在しましたが、美濃国の斎藤氏とは同盟関係にありました。
信長は斎藤道三の娘である濃姫を正妻に迎え、斎藤氏との友好関係を維持していました。この同盟関係は、信長にとって大きな利点でしたが、それでも他の敵対勢力の存在は大きな脅威として立ちはだかっていました。
鳴海城主・山口教継の裏切り
家中で予感していた事態が現実となりました。信長が織田弾正忠家を継いでからたった1か月後、鳴海城(現在の緑区)の城主、山口教継が反旗を翻しました。教継は今川氏と手を結び、援軍を呼び入れたのです。
そして、息子の九郎二郎を鳴海城の守将として配置し、笠寺(現在の南区)に砦を築いて今川の5人の将を配置しました。自身は中村にある砦の守備を固めました。
4月17日、信長は鳴海城に向けて出陣し、古鳴海の三の山に陣を取りました。信長の軍勢は約800人でした。一方、九郎二郎は約1500人の兵を率いて鳴海城を出陣しました。これを見た信長も三の山から動きました。
赤塚の戦いの展開
軍勢の布陣と兵力差
両軍は赤塚の地で衝突しました。戦いは接近戦となり、混乱の中で兵士たちが入り乱れました。矢に射られて落馬した者を双方の兵士が引っ張り合う場面も見られました。
山口の兵士たちも、つい最近まで織田家に従っていた者たちであり、お互いに顔見知りの者が多くいました。それにもかかわらず、戦いは容赦なく続き、信長側だけでも30人が討ち死にしました。
激しい接近戦と引き分け
赤塚の戦いの最中、多くの駆け引きが繰り広げられましたが、最終的にどちらの勢力も決定的な勝利を収めることができませんでした。戦いは長引き、結果的には信長も敵軍も引き分けを選び、それぞれの軍を退くことになりました。
さらには、捕虜の交換や馬の返還などの取り決めも行われ、その様子は「なれ合い」に近いものでした。
合戦後の影響
赤塚の戦いは、信長にとってリーダーシップを試される場でありながら、結局その力を十分に示しきれない結果に終わりました。この時点ではまだ彼の指導力には課題が残され、家臣たちの不安は拭えなかったと言えるでしょう。
ここからは、憶測に過ぎませんが、相手にかつての味方がいたことから、勝利したとしても、後味の悪い勝利だったことでしょう。負けもせず勝ちもしないことが、最善だったと言えます。
信長は、引き分けという最善の道を、あえて選んだのかもしれません。
信長と現代のリーダーシップ
信長の初戦は最善の策だったかもしれない、とはいえ引き分けに終わり、成功とは言えませんでしたが、その後は、自ら指揮した多くの戦いで、多くの勝利をおさめています。
現代のビジネスシーンにおいても、リーダーとなった初めての挑戦で、思うような結果を出せなくても、それに臆することなく教訓に変えて、次の成功に活かすことが重要だと言えるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。