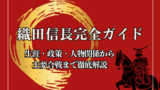こんにちは。戦国時代大好き「お春」です。
織田信長を輩出した織田氏はどういう一族だったのでしょう? 今回は、織田信長と織田家について解説していきます。
織田信長と織田家の成り立ち【基礎編】

守護代の家臣から戦国大名へ!織田家の大躍進
織田氏は、尾張の守護代を務めていました。平家の末裔とされる説もありますが、実際には越前国織田庄の庄官の末裔が守護の斯波氏の家臣となった一族と考えられています。
織田氏は応仁・文明の乱(1467年~1477年)以降、尾張の守護代を務めるようになりましたが、伊勢守家と大和守家に分かれていきました。信長の家系は、後者の家臣である織田弾正忠家に属します。
信長の父・信秀(1496年または1508年〜1551年)は、織田弾正忠家を大いに躍進させました。彼は23人の子をうまく配置し、東は今川、西は斎藤と戦いながら尾張中心部へ進出しました。また、信長の妻として斎藤道三の娘を迎えることで政治的な結びつきを強化しました。
織田信長の天下統一に向けた動き【発展編】
尾張統一と桶狭間の戦い
信長は天文3年(1534年)に誕生し、織田一族との戦いを経て尾張を統一しました。その後、桶狭間の戦い(1560年)で今川義元を破り、美濃へ進出します。さらに、足利義昭を擁して上洛し、覇権争いに一歩先んじる存在となっていきました。

信長が天下統一事業を支えた家臣団の特徴は、以下の3つにまとめられます。
革新的軍事改革①:兵農分離
信長は、地侍や土豪を専業武士として自分のもとに引き寄せました。それにより、土地に縛られず、常時出陣可能な体制を整えました。この革新的な兵農分離により、信長の軍隊は常に訓練された強い兵士を維持することができました。
革新的軍事改革②:実力主義
信長は家柄や縁故を重視せず、有能な人物を大胆に起用しました。羽柴秀吉や明智光秀など、出自がはっきりしない人物も軍団の中核に育て上げました。こうして適材適所に人材を配置することで、織田家臣団の強化を図りました。
革新的軍事改革③:与力制
信長は、旗頭となる重臣とその下に直接従属する旗本を配する与力制を導入しました。たとえば、柴田勝家に前田利家を従属させるなど、このシステムにより合理的な軍団統制が可能となりました。旗頭が戦死しても、与力たちは再編成できるため、軍団の柔軟性と持続力が高まりました。
実力主義の人材登用と天下統一を目指した方面軍【実践編】
信長の初期家臣団とその統率
信長が最初に統率した家臣団は林秀貞、平手政秀、青山信昌、内藤勝介などでした。しかし、兄弟や譜代の家臣たちが反旗を翻すこともあり、信長は彼らを鎮圧しつつ、新しい人材の登用を進めました。特に羽柴秀吉などが新勢力として台頭していきました。
御馬廻衆と方面軍の編成
信長の親衛隊として、赤母衣衆や黒母衣衆が結成されました。彼らは信長の身辺警護や伝令、巡回役を務めました。また、美濃攻略や上洛の過程で新たな武士たちが加わり、家臣団が強化されていきました。
天正元年(1573年)には、全国展開を視野に入れた家臣団再編成が行われ、5つの方面軍が編成されました。
- 信忠を旗頭とする武田軍対抗軍団
- 柴田勝家の北陸方面軍
- 明智光秀の山陰・近畿方面軍
- 羽柴秀吉の中国方面軍
- 滝川一益の関東方面軍
さらに、丹羽長秀や池田恒興らが遊撃軍として配置され、四国方面軍も編成されていました。
非情なる実力主義の影響
信長は適材適所の人事を行い、家臣団を統率していましたが、その反面、無能な者は容赦なく切り捨てました。佐久間信盛親子や林秀貞などの長老クラスも追放されました。特に信盛は本願寺攻略に失敗し、その責任を問われて追放されました。
この厳しさが、結果として家臣らの不安をあおることになり、最終的には天正10(1582)年6月2日の本能寺の変で明智光秀の謀反を招く結果となりました。実力主義の徹底が、信長の失脚へとつながった可能性もあるのです。
織田信長と織田家に関するよくある質問
- Qなぜ織田信長だけが天下統一に近づけたのですか?
- A
織田信長が他の戦国大名より優位に立てた理由は、主に3つの革新的な改革にあります。
- 兵農分離の徹底実施 – 農民と武士を完全に分離し、専業軍人による常備軍を創設
- 徹底した実力主義 – 家柄や血縁に関係なく、能力のある人材を大胆に登用
- 合理的な軍団編成 – 与力制による効率的な指揮系統と方面軍制度
これらの改革により、織田軍は他の大名軍よりも強力で機動性の高い軍隊となり、連戦連勝を重ねることができました。特に桶狭間の戦い以降、この軍事的優位性が決定的となりました。
- Q兵農分離はいつから始まり、どのような仕組みだったのですか?
- A
織田信長の兵農分離は1560年代後半から本格化しました。
従来の制度:
- 農繁期には戦争を中断(農民兵が田畑に戻る必要があった)
- 季節限定の軍事活動
- 農業と軍事の両立による効率の悪さ
信長の兵農分離後:
- 武士は城下町に居住し、専業軍人として訓練
- 農民は農業に専念し、年貢で武士を養う
- 一年中いつでも出陣可能な常備軍の実現
- 高い練度と統制力を持つ職業軍人の誕生
この制度により、織田軍は他の大名軍が農繁期で動けない時期でも積極的に軍事行動を取ることができ、大きな戦略的優位性を獲得しました。
- Q織田家の家系はどのような出自だったのですか?
- A
織田氏の出自については複数の説がありますが、越前国織田庄出身説が最も有力です。
織田氏の系譜:
- 平安時代後期 – 越前国織田庄の庄官として活動
- 鎌倉時代 – 斯波氏(足利一門)の家臣となる
- 室町時代 – 尾張守護代に任命される
- 戦国時代 – 織田弾正忠家から信長が台頭
織田氏の分家:
- 織田伊勢守家 – 尾張上四郡の守護代
- 織田大和守家 – 尾張下四郡の守護代
- 織田弾正忠家 – 大和守家の家臣(信長の家系)
信長の祖父・信定、父・信秀の代に急激に勢力を拡大し、本来は「家臣の家臣」だった弾正忠家が戦国大名へと成り上がりました。これも実力主義の表れと言えるでしょう。
- Q織田信長の後継者問題はどうなっていたのですか?
- A
信長は長男・織田信忠を後継者として育成していました。
信忠の経歴と実績:
- 1557年生まれ – 信長の嫡男
- 1574年 – 元服し初陣を飾る
- 1575年 – 長篠の戦いで武功
- 1580年 – 岐阜城主として美濃を統治
- 1582年 – 武田征伐の総大将として大勝利
後継者としての準備:
- 方面軍の一つ(対武田軍団)の総指揮官
- 美濃国の統治経験
- 主要な戦いでの指揮経験
本能寺の変での運命: 残念ながら信忠も本能寺の変の際に京都の二条城で明智軍と戦い、父・信長と運命を共にしました。これにより織田家の後継問題が複雑化し、最終的に羽柴秀吉が天下を取る結果となりました。
まとめ
織田信長の天下統一への道のりは、その軍事力と戦略的な人材登用によって支えられていました。信長の革新的な兵農分離、実力主義、そして合理的な軍団編成は、織田家を強大にしました。しかし、その非情さが最終的には自身の死を招く結果となり、信長の物語は終わりを迎えました。
現代においても、斬新な改革には困難がつきまといます。例えば大阪都構想の頓挫などが挙げられます。強引に進めようとすれば、既得権益の持ち主から抵抗に遭い、足を引っ張られることもあります。織田信長と織田家の物語の教訓として、改革には先へ先へと事を進めるカリスマ性と、バランス感覚、またはバランス感覚を持った調整役が必要だということが分かります。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。