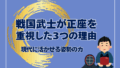戦国の世を生きた武士たちが相撲に熱中した理由とは?
「相撲」と聞くと、現在では国技としての華やかな土俵や横綱の姿が思い浮かぶかもしれません。しかし、その源流をたどっていくと、戦国時代の荒々しくも格式ある相撲の姿が浮かび上がってきます。
なぜ、戦乱の続いた戦国時代に、武士たちは相撲を愛し、取り組んでいたのでしょうか?
実は相撲は、単なる娯楽ではなく、武士の戦闘訓練・精神鍛錬・神事との結びつきなど、多面的な役割を担っていました。
この記事では、戦国時代における相撲の位置づけとその文化的背景、さらには現代相撲への影響までを、歴史的資料とともに丁寧に紐解いていきます。
戦国時代における相撲の起源と発展
日本の相撲の歴史は非常に古く、『日本書紀』によれば、相撲の最古の記録は紀元前23年の「野見宿禰(のみのすくね)」と「当麻蹴速(たいまのけはや)」の戦いにさかのぼるとされています
この出来事は神話的な要素を含みつつも、相撲が神事や儀式と密接に結びついていたことを示しています。
中世に入り、相撲は朝廷や寺社での儀式的要素を持ちつつ、武士階級へと広がっていきます。特に戦国時代には、相撲が実戦的な鍛錬としての性格を強め、武士たちの間で盛んに行われるようになります。
織田信長や豊臣秀吉の記録にも「相撲見物」の記載があり、彼らが自ら相撲大会を催したことが分かっています。つまり、戦国時代の相撲は「神事」から「軍事訓練」へと変化を遂げながら、多くの意味を持つ武芸へと昇華していったのです。
武士たちの力試しとしての相撲
戦国時代は、常に戦の準備が求められる厳しい時代。武士たちは日々、槍術や剣術だけでなく、体術の鍛錬にも励んでいました。そこで「素手での組討ち」としての相撲は、極めて実践的な鍛錬法だったのです。
相撲では、以下のような力が試されました:
- 筋力・体幹の強さ
- 相手の重心を読む力
- 瞬時の判断力
- 転倒や掴みの技術
これらは戦場においても重要なスキルであり、「一騎打ち」に備えるための訓練として相撲は重宝されました。特に、合戦前に行われる相撲試合は、兵士の士気を高める場でもあったのです。
また、戦国大名の間では、力自慢の家臣を他家に誇示するための相撲披露も行われていました。武士にとって相撲とは、名誉と誇りをかけた戦いでもあったのです。
戦国時代の相撲大会とその社会的意義
戦国時代の相撲大会は、単なる武芸披露ではなく、政治的・宗教的・娯楽的な多様な側面を併せ持っていました。
特に有名なのが、織田信長が安土城で催した「天下一相撲大会」です。この大会では、各地から力自慢の相撲取りが集められ、信長の権威を示す場として活用されました。
このような大会は次のような意義を持っていました。
- 家臣や民衆の結束を高める
- 領主の権威を示す
- 戦の前の士気高揚
- 地域交流の機会としての娯楽
また、神社の祭礼と結びついた相撲大会も多数存在し、地域の伝統行事としての価値も生まれていきます。
相撲と神事の関係

相撲のルーツは神事にあります。これは戦国時代になっても変わらず、五穀豊穣や無病息災を祈る「奉納相撲」が各地で行われていました。
神社の境内に土俵を設け、神前で行われる相撲は、神々への感謝や祈願の手段とされ、「神と人とをつなぐ神聖な儀式」でもありました。
有名な例としては、伊勢神宮の奉納相撲や、出雲大社の神在祭での相撲などがあり、これらは今もなお伝統行事として受け継がれています。
つまり、戦国時代の相撲には、武芸としての側面と神聖な儀式としての側面が共存していたのです。この「武と神」の融合が、日本独自の格闘技文化の深みを形づくっていきました。
相撲の技術と武士道精神
相撲は単に力比べの競技ではありません。礼に始まり礼に終わる精神性、そして正々堂々と戦う姿勢は、まさに武士道そのものです。
戦国時代の武士たちは、以下のような価値観を相撲から学んでいました:
- 礼節と規律
- 自己抑制と精神統一
- 勝敗に対する潔さ
- 相手への敬意
これらはすべて、武士道の核心とも言える教えです。
特に、戦場での勝敗が命に直結する中で、「潔く勝ち、潔く敗れる」という心構えは、相撲を通して日常的に養われていたのです。
また、相撲の型や技術にも、相手を痛めつけるのではなく「崩し、投げる」「制する」ことを重視する点に、武士道の慈悲と美学が表れています。
戦国時代の相撲が現代に与えた影響
現代の大相撲は、江戸時代に制度化され、興行として発展しましたが、その土台には戦国時代に培われた武士文化としての相撲が存在します。
たとえば:
- 土俵入りや塩撒きなどの所作には神事の名残が色濃く残っている
- 礼節重視の精神性は今も力士に求められる資質
- 相撲を通じた心身の鍛錬という価値観は、スポーツ教育にも通じる考え方
また、相撲をテーマにした伝統芸能や地域行事の多くが、戦国〜江戸初期の文化を受け継いでおり、日本文化の中核として相撲が位置づけられていることがわかります。
現代人が相撲に感動し、尊敬の念を抱くのは、単なる格闘技としてではなく、長い歴史の中で育まれた精神文化を感じ取っているからかもしれません。
まとめ:相撲に映る戦国武士の魂と日本文化の本質

戦国時代の相撲は、単なる娯楽や格闘技ではありませんでした。
それは、武士たちの戦いの準備であり、精神修養であり、神への祈りでもあったのです。
- 武士たちは相撲で己の力を試し、心を磨いた
- 相撲大会は政治的・宗教的な行事としても機能した
- 礼節や武士道精神が、今の相撲にも息づいている
現代の相撲を見つめるとき、私たちはただのスポーツではなく、過去から受け継がれた“魂の格闘”を目にしているのかもしれません。
相撲を通じて、戦国時代の武士たちがいかに生き、戦い、祈ったのかを知ることは、日本人のルーツを見つめ直す旅でもあります。
それこそが、時代を超えてなお、人々が相撲に魅了され続ける理由なのです。