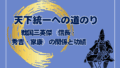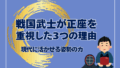戦国時代――陸の戦国武将たちが繰り広げた合戦の数々は多くの人の記憶に刻まれていますが、海を制する者たちの物語は、まだまだ語られ尽くされていません。
瀬戸内海を駆け抜けた村上水軍、鉄甲船をもって革新をもたらした九鬼水軍、そして全国に点在していた地方水軍たち。彼ら“海の武士”がいなければ、戦国の歴史はまったく違ったものになっていたかもしれません。

この記事では、戦国時代の海戦において絶大な影響力を誇った水軍武将たちの活躍を、ランキング形式とともに徹底解説。海戦という特殊な戦場で発展した戦術・兵器、歴史を動かした名勝負、そして今なお各地に残る“水軍の記憶”までを網羅的にご紹介します。
「村上水軍ってどれだけ強かったの?」「鉄甲船って本当に最強だった?」「他にも隠れた英雄はいるの?」そんな疑問を持つあなたへ、知っているようで知らない戦国水軍の真実をお届けします。
知識欲を刺激し、そして少し胸が熱くなる――そんな「海の戦国史」を、今こそ掘り起こしてみましょう。

この記事の内容が楽しく理解できるポッドキャストを作成してみました。
戦国時代の水軍とは?海の戦国史入門
水軍が果たした重要な役割
戦国時代の日本は、陸上の戦いだけでなく、海上でも激しい争いが繰り広げられていました。特に瀬戸内海や伊勢湾、九州北部などの海域では、水軍の力が戦局を大きく左右しました。海上輸送の確保、敵勢力の補給線遮断、さらには城や港の攻防戦など、水軍はまさに「動く要塞」として機能していたのです。
水軍の存在なくして、豊臣秀吉による西国統一も、毛利家の拡大もあり得なかったといっても過言ではありません。海上の制海権を握ることは、陸上の覇権へとつながる重要なファクターだったのです。
陸上戦との違いと特殊性
水軍戦の特徴は、まず何と言ってもその「流動性」にあります。陸戦では考えられないスピードで部隊を移動させたり、奇襲を仕掛けたりできるのが水軍の強みです。また、船の性能や編成、潮の流れや風向きといった自然条件も戦局に影響を与えるため、戦術の幅が広く、知略が求められました。
さらに、海戦では火器や火薬を使った戦いがいち早く導入された点も特筆すべきです。焙烙火矢や火船といった特殊兵器は、海上戦ならではの発明であり、戦国時代の戦術的進化を象徴しています。
戦国最強!日本三大水軍の実力ランキング

第1位:村上水軍(瀬戸内海の覇者)
村上水軍は、能島・来島・因島の三家からなる連合勢力で、瀬戸内海を実質的に支配していた海の覇者です。その航海技術と戦闘力は他の追随を許さず、各地の大名たちにとっては頼もしい味方であり、時に手強い敵でもありました。
特に村上武吉の時代には、その海上戦術が洗練され、瀬戸内海全域での影響力を誇るまでに成長。毛利家との同盟を通じて西国の制海権を掌握し、後の海戦でも数々の功績を残しました。
第2位:九鬼水軍(鉄甲船の革命者)
伊勢志摩を拠点とする九鬼水軍は、九鬼嘉隆の指揮のもと、織田信長や豊臣秀吉に仕え、画期的な鉄甲船を開発・運用したことで有名です。
特に第二次木津川口の戦いでは、毛利水軍の焙烙火矢攻撃を完全に封じ込め、戦況を一変させました。鉄板で装甲された船は世界的にも画期的であり、海戦の常識を覆す革新として、後世に語り継がれています。
第3位:松浦党(西国の海賊衆)
九州北部を中心に勢力を張った松浦党は、古くから海運・交易を担いながら、時に武装して戦う海賊衆として活躍してきました。特に対馬・壱岐とのつながりが深く、朝鮮半島や中国大陸との交易ルートを掌握していた点が他の水軍と一線を画しています。
戦国期には大友氏や龍造寺氏と協力しつつ、海戦にも多く参戦。その経験値と実戦能力は極めて高く、「西国の外洋型水軍」として評価されています。
海戦を変えた革命的な水軍武将たち

九鬼嘉隆:鉄甲船で毛利水軍を撃破した天才
九鬼嘉隆(くき よしたか)は、九鬼水軍を率いた戦国屈指の海戦武将です。彼の最大の功績は、なんといっても鉄甲船の開発と実戦投入。特に1578年の第二次木津川口の戦いでは、木製船主体の毛利水軍に対して圧倒的な防御力と火力を誇る鉄甲船を用い、海戦の常識を一変させました。
信長からも高く評価され、のちには秀吉の朝鮮出兵にも従軍。実戦経験と革新的な技術力を兼ね備えた“海のエンジニア武将”ともいえる存在です。
村上武吉:瀬戸内海を支配した海賊王
村上武吉(むらかみ たけよし)は、能島村上家の当主として、瀬戸内海を支配した“海賊王”の異名を持つ人物です。彼のもとで村上水軍は勢力を拡大し、海賊行為と保護貿易を巧みに使い分ける高度な戦略で西日本の海を掌握しました。
特に第一次木津川口の戦いでは、毛利水軍とともに織田勢を圧倒し、制海権の重要性を証明。その後も毛利家と協調しつつ、数々の海戦で戦果を挙げました。
来島通総:機動力で勝負した戦術家
来島通総(くるしま みちふさ)は、村上三家の一つ、来島家の名将であり、戦術的な機動力に優れた指揮官として知られています。特に小早船を駆使した高速奇襲や、入り組んだ瀬戸内海の地形を活かした遊撃戦術で敵軍を翻弄しました。
織田軍との戦いや、豊臣政権下での朝鮮出兵にも参戦。戦術眼と統率力に秀でた実力派武将として評価されています。
歴史を変えた決定的な海戦5選

厳島の戦い(1555年):毛利元就の奇襲作戦
毛利元就が陶晴賢を破ったことで知られる厳島の戦いは、水軍の戦術が大きく影響した海陸複合戦でした。毛利軍は地の利と天候を利用し、奇襲によって陶軍を壊滅に追い込みました。
この戦いでは、村上水軍を中心とした海上輸送・支援が勝敗を分ける決定打となっており、海戦の意義を歴史に刻んだ一戦といえます。
第一次木津川口の戦い(1576年):村上水軍の完勝
織田信長の石山本願寺包囲に対して、毛利方の水軍が反撃した海戦です。村上水軍を含む毛利連合水軍が、織田方の制海権掌握を阻止し、補給路を確保することに成功しました。
この戦いでは、奇襲・小型船の活用・火器の運用など、水軍戦の基本戦術がフル活用され、まさに戦国水軍の真価が発揮されました。
第二次木津川口の戦い(1578年):鉄甲船の逆襲
第一次の敗北を受け、織田信長は九鬼嘉隆に鉄甲船の建造を命じます。この船が威力を発揮したのが、第二次木津川口の戦いです。
焙烙火矢を主力とする毛利・村上連合水軍の戦術を、鉄板で装甲された船が無力化し、圧倒的な火力で逆襲。結果、織田方が制海権を奪取し、石山本願寺包囲が加速しました。
小牧・長久手の戦いの海戦(1584年)
一般的には陸戦として知られる小牧・長久手の戦いですが、実は三河湾周辺では水軍同士の小規模な海戦も行われていました。
特に九鬼水軍や松浦党が関与し、局地的ながらも制海権の奪い合いが展開され、海と陸の連携戦の一例として注目されています。
朝鮮出兵での海戦(1592-1598年)
豊臣秀吉による文禄・慶長の役では、日本水軍が大規模に海外派兵されました。村上・九鬼・脇坂らの水軍が朝鮮半島沿岸に出兵し、李舜臣率いる朝鮮水軍と激突。
亀甲船など革新的な戦術を持つ朝鮮側に苦戦を強いられるも、日本側も最新の装備と経験で応戦。海戦史における国際的な技術と戦略のぶつかり合いが展開されました。
戦国水軍の革新的戦術と兵器

鉄甲船:世界初の装甲艦の設計思想
鉄甲船とは、船体に鉄板を貼り付けて敵の火矢や砲撃から身を守るという、当時としては画期的な防御構造を備えた戦闘艦です。九鬼嘉隆が信長の命により建造し、第二次木津川口の戦いで初実戦投入されました。
これは世界的にも早期の装甲艦の事例として知られ、単なる防御だけでなく、鉄砲などの火力を効果的に運用できるプラットフォームとして海戦の概念を一変させました。
焙烙火矢:海戦用火器の進化

焙烙火矢(ほうろくひや・焙烙玉)は、火薬や油を詰めた小型の爆発物を敵船に投げ込む兵器で、主に村上水軍や毛利水軍が使用しました。接近戦では非常に効果的で、木造船を炎上させ、混乱を引き起こす強力な武器でした。
火矢と異なり、爆発と延焼を同時に狙えるため、戦術の幅を広げる兵器として重宝されました。焙烙火矢の活用は、戦国時代の火薬技術の高度化を物語っています。
関船・小早船:用途別艦船設計
関船(せきぶね)は大型で装甲の厚い戦闘船で、兵士の搭乗数も多く、主に正面衝突や砲撃戦に使われました。一方、小早船(こばやぶね)は小型軽量で速度に優れ、偵察や奇襲に活用されました。
水軍はこの2種の艦船を組み合わせて戦術を展開し、柔軟かつ多彩な作戦行動が可能となったのです。これらの艦船設計は、海戦における艦隊戦術の原点ともいえるでしょう。
火船戦術:決死の特攻作戦
火船戦術とは、火薬や油を積んだ無人の船を敵船に向かって突入させて爆発・炎上させるという、まさに“水上のカミカゼ”とも言える戦法です。
成功すれば敵艦隊に甚大な損害を与えることができましたが、風向きや潮流を読み切る高度な判断力が求められるため、使用には熟練の技術が必要でした。戦国時代の水軍はこのような高リスク・高リターンな戦術も果敢に取り入れていたのです。
知られざる地方水軍の英雄たち

熊野水軍と堀内氏善
紀伊半島の南端、熊野地方に拠点を置いた熊野水軍は、かつて熊野信仰の護送役として発展した水軍です。その中でも堀内氏善(ほりうち うじよし)は、織田信長や豊臣秀吉に仕え、熊野水軍を戦国大名の軍事力の一部として組織化しました。
堀内氏は航海術と船の操縦技術に優れ、紀伊・伊勢湾・四国沿岸にかけて活躍。特に秀吉の九州平定や朝鮮出兵において重要な役割を果たしました。地形を熟知した“ローカルな機動力”を活かした戦いぶりは、水軍戦術の奥深さを物語っています。
武田水軍:山国の意外な海軍力
意外にも内陸の国・甲斐を本拠とした武田氏も、水軍を保持していました。武田信玄は駿河湾を押さえるべく駿河の今川氏を攻略し、海へのアクセスを確保。その後、安宅船などを用いた水軍の整備を進め、遠江や駿河の沿岸部に展開しました。
特筆すべきは、駿河湾から三河湾までの補給線の確保に成功し、織田信長の勢力拡大を一時的に食い止めた点。山国の武将が海戦にまで関与した好例といえます。
伊豆水軍:北条氏の海上戦力
伊豆半島を本拠とする伊豆水軍は、後北条氏の海上戦力として相模湾・駿河湾を中心に活動しました。特に北条氏康のもとで強化され、関東から東海地域の制海権確保に尽力しました。
伊豆水軍の特徴は、小回りの利く船を多数保有していた点と、房総半島や伊豆諸島まで勢力を伸ばした点にあります。情報伝達・補給・奇襲と多様な任務をこなし、陸上戦を支える陰の立役者となりました。
河野水軍:四国の海の守護者
伊予国(現在の愛媛県)を本拠とした河野氏もまた、有力な水軍を有していました。特に村上水軍との関係が深く、連携して瀬戸内海西部の制海権を維持していました。
河野水軍は、豊後の大友氏や毛利氏との関係を巧みに調整し、時には独自の外交戦略を展開。四国の海上交通を掌握しつつ、西日本のパワーバランスを維持する役割を担っていたのです。
このように、中央政権に組み込まれていない地方水軍であっても、それぞれの地理的・戦略的条件に応じた役割を果たし、戦国海戦史の一翼を担っていたのです。
水軍武将たちのその後と現代への影響
豊臣秀吉の海賊禁止令(1588年)
戦国期を通じて猛威を振るった水軍勢力も、秀吉の全国統一に伴い大きな転換点を迎えました。その象徴が1588年に発布された「海賊停止令(海賊禁止令)」です。これにより、私的な海上武力の行使が禁じられ、水軍は軍事組織としての役割を徐々に終えることになります。
この政策の背景には、統一政権による海上秩序の確立と、海外交易の管理強化がありました。特に村上水軍は、この令により活動を大きく制限され、一部は陸上武士として再編されていきました。
江戸時代への移行と水軍の変化
江戸時代に入ると、平和な時代が到来し、水軍そのものの存在意義が希薄になっていきます。旧水軍勢力は幕府直轄の海防要員や、海上警備、沿岸地域の管理役などに転身。海戦のための部隊ではなく、海の秩序維持を担う存在へと役割を変えていきました。
たとえば、九鬼家は江戸幕府下で紀伊・志摩地域の海防を担う家柄として存続し、村上家も一部が旗本として仕え、伊予松山藩などに取り込まれていきました。
現代に残る水軍文化と観光地
今日においても、戦国水軍の歴史と文化は各地に息づいています。愛媛県今治市の「村上海賊ミュージアム」や、和歌山県の「熊野水軍埋蔵文化財センター」など、観光と学術の両面で注目を集める施設が点在しています。
また、来島海峡や瀬戸内の多島美といった景観そのものが、かつての海戦の舞台でもあり、観光ルートや船旅として整備される例もあります。地域振興と結びついた「水軍ブランド」の活用は、現代でも歴史の価値を活かす取り組みとして定着しつつあります。
さらに、小説・ドラマ・ゲームなどのエンターテインメント分野でも、村上水軍や九鬼水軍は人気題材として扱われており、戦国の“海の英雄たち”は今なお多くの人々に感動を与え続けています。
まとめ:戦国水軍武将から学ぶ海戦の教訓

戦国時代の水軍武将たちは、単なる「海の兵力」ではなく、戦略・技術・情報・外交といった多角的な能力を備えた存在でした。
村上水軍のように地形と航路を掌握して制海権を維持した例、九鬼水軍のように革新的な兵器で戦局を一変させた例など、彼らの活躍は現代にも通じる教訓を多く含んでいます。
第一に学べるのは「環境適応力」です。海上という不安定な戦場で成果を上げるためには、潮流や風、船の性能、敵の動きを総合的に判断する柔軟な思考と現場対応力が必要でした。現代においても、急激な変化に柔軟に対応する姿勢は、ビジネスや社会活動において重要な資質です。
第二に、「技術革新と戦術の融合」が挙げられます。鉄甲船や焙烙火矢、火船戦術など、常識にとらわれない発想が新たな勝利を生み出しました。これは現代でいえば、イノベーションやテクノロジーをどう活用し、既存の仕組みをどう突破するかという課題にも通じます。
そして第三に、「連携と信頼の重要性」です。村上水軍と毛利家、河野水軍と他国勢力など、戦国期の水軍は単独ではなく、常に他者との連携をもとにその力を発揮していました。これは組織運営やプロジェクトマネジメントにおいても非常に示唆的です。
かつて海を駆け抜けた戦国水軍武将たちの知略と勇気は、歴史の彼方に消えたわけではありません。私たちはその姿から、今を生き抜くヒントを得ることができるのです。海戦の記憶は、現代の私たちの中にも確かに息づいています。